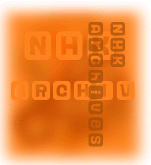
![]()
- シリーズ「戦争の記憶を伝える」が放送されています。例年、この時期になると、特集されるテーマですが、現在の特集と見比べるのも面白そうです。
-
9月はいろいろ、あって放送もままならなかったようですが、10月はテーマが「熱き時代に」と決定して、7日は山口百恵、篠山紀信関係のN特を放送するそうです。楽しみ。
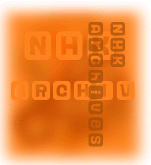 |
|
05.08.01
|
15.07.01 「ドキュメンタリー 富谷国民学校」(1969年8月29日放送)をはり。 この放送は集団疎開について撮影されたフィルムを復活させ、そこから映し出された映像と、現在もある富谷小学校の新入生と、その親であり、当時、児童として、集団疎開した人々の記録である。 //もちろん、わたしは戦後生まれで、戦中の経験などない。瓦礫と言ったら、阪神淡路大震災を思い出すくらいだ。それも、当事者ではない。俯瞰して、或いは間近に第三者として、見ただけである。それでも、無駄に多くのことばで綴りたい。何か、そう思う今日この頃なのである。 |